※この記事は2015年に軍装操典に掲載されました。
兵隊時代
徴兵は本籍の堺市で行われます。父は新設の三ケタ連隊の一つに入りました。大阪の連隊は精兵とは言えなかたそうで、「またも負けたか八連隊」と言われていたそうです。内地での訓練期間が終了すると、中国戦線で戦っている中隊に補充兵として8名ほどで派遣されました。
指示された船、列車、トラックを乗り継いで中隊を追いかけましたが、最前線で戦っている中隊までは追いつけず、とある中国の補給線途中の丘の上で中隊が戻ってくるのを待つ様に命令されました。3日分の食料を支給されましたが、何日間で中隊と合流できるか見当が付きません。補充兵は全員新兵の二等兵でしたが、専門学校を出ている父が指揮を取る事となりました。まず、いつ中隊と合流できるか判りませんし、その間の食料の補給が不明でした。この3日分の食料で食いつながなくてはならないと、粥にして1週間持たせることとしました。幸い春先で、丘は山菜のワラビで埋め尽くされていました。ワラビを取っては茹でて食べましたが、調味料が無い為、数回食べると生臭くて喉を通らなくなります。幸い雉を見つけて三八銃で捕獲し、丘の下を通る輜重部隊に塩と交換してもらいました。これで何とかワラビに味を付けて、食べられるようになりました。三八銃で雉を捕獲するのは銃弾の無断使用で、違反でしたが、この辺の父は要領が良く、「不審な中国人を見つけ、誰何したら発砲してきたので撃ち返すと逃げました」と報告したそうです。
結局、3日分の食料で10日以上過ごしました。ワラビばかりの毎日だったそうです。新兵で早くも帝国陸軍の補給の悪さと、空腹を体験したそうです。ワラビは一生分食べたと言っていました。戦後も山菜そばなどは、絶対注文しない父でした。
やがて伝わってきたのは、日本軍が中国軍に大敗北したと言う情報でした。日本軍の大部隊が父のいる丘の下の道を次々に通り、日本軍はこんなに戦車を持っていたのかと呆れるほどの数の戦車が通過して行きました。やがて父の連隊は最後尾で退却してきました。いや、転進してきました。中隊長以下30名ほどで、全員軽機関銃、擲弾筒で武装しています。さすが最前線の中隊は装備が違うと感心して、中隊長に補充兵として到着した申告を致しました。
日本軍は大敗北をして、父の所属する予定の中隊は、200名が30名まで減っていました。戦死した兵士の三八式歩兵銃は10丁程を束にして、中国人クーリーに担がせていました。軽機関銃、擲弾筒等の火器だけを生き残った日本兵で担いで持って帰ったと言う状況でした。父の申告に対して、中隊長は「うん・・・」と言っただけで、衰弱しきっていました。
日本軍は転進を続けました。父は最後尾の殿軍となり、落後した日本兵が道端でうずくまっているのを立たせてビンタをくわせて気合いを入れ、無理やり歩かせました。相手の階級が下士官であろうと、お構いなしでした。父の後ろには日本軍は居ませんので、このまま残せば捕虜となる道しか残っていません。
数日の行軍後宿営地まで戻りました。中隊は30名まで減っていましたので、夜の衛兵番は父たち初年兵の役割でした。昼は昼で訓練があり、夜は人数が少ないので衛兵番が通常より長く続きます。1週間もすると体力の限界を超えて、精神的疲労も激しく、何をしているのか判らない状態になりました。ある夜、警戒線に立って不審番をしている時、自分が持っているのが三八式歩兵銃で無く、箒である事に気が付きました。衛兵番を交代する時、お互いに申告しますので、相手が気が付かない訳がありません。相手の兵士も過労で気が付かなかった様です。そっと宿舎に戻り、箒を戻して三八式歩兵銃に持ちかえました。幸い誰にも気が付かれませんでしたが、見つかれば処分は免れなかったでしょう。
陸軍予備士官学校
本来陸軍士官は、幼年学校、予科士官学校、士官学校卒業後に少尉任官し、陸軍大学校を卒業したら将官への道が開けます。また、漫画「のらくろ」の様に、下士官から将校となり大尉で定年を迎える制度もありました。
支那事変の勃発とともに、兵科下級将校が大量に不足してきました。従来の幹部候補生として部隊内での教育では間に合わなくなり、幹部候補生を集合教育して将校に養成する予備士官学校制度が出来ました。父は志願して豊橋予備士官学校に入学いたしました、1年弱の教育期間で将校に任官できます。
豊橋は下士官教育を目的とした、陸軍教導学校がありました。昭和13年、陸軍予備士官学校令で豊橋陸軍教導学校は、豊橋陸軍予備士官学校となりました。父は昭和15年頃、豊橋予備士官学校に入校いたしました。豊橋市の南部は広く演習場が広がり、渥美半島を1周する行軍があったり、演習場で訓練する毎日でした。
正月の1月1日も訓練はありました。豊橋から豊川稲荷まで行軍して、参拝し、昼はお汁粉まで振舞われて、今日は天国と思っていたそうです。帰りに豊川に差し掛かった時、教官から豊川の渡河偵察を命じられました。生徒は川岸を各所に走り回って、渡河の出来そうな場所を見つけて、教官に報告しました。
「馬鹿もの!!」教官の一喝がありました。「将校偵察は、大隊、連隊、ひいては師団の渡河を決める重要な偵察である。貴様らは河にも入らないで渡河地点を決めるとは何事か。本日は正月である。格別の温情を持って、服を脱いで渡河調査をして良し! かかれ! 」全員川岸で軍服を脱いで、ふんどし一つで寒空の豊川に入って対岸まで渡って、渡河地点を確認して報告したそうです。父は、あの時は寒かったけれど、将校偵察の重要さが身に付いたと言っていました。おそらくは教導団時代からの恒例行事だったのかもしれませんが、身にしみて学ぶことが出来たそうです。
→将校として中国戦線へに続く
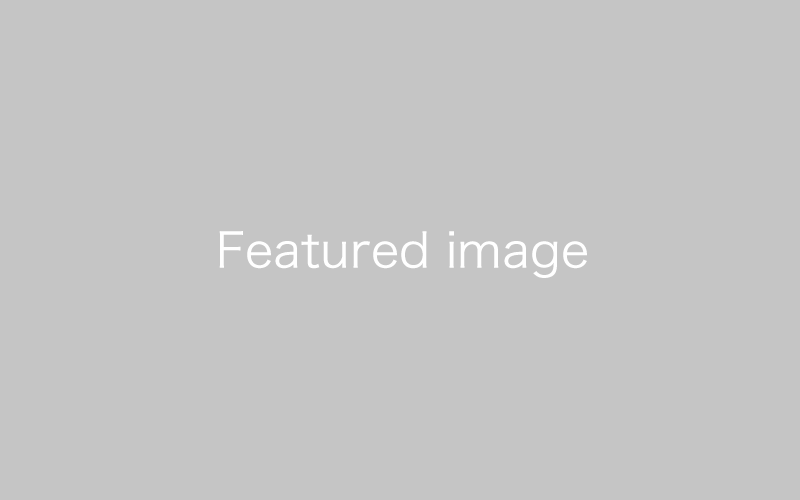


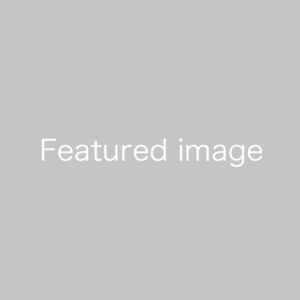
コメント