※この記事は2015年に軍装操典に掲載されました。
今年は戦後70年目となり、戦前、戦時の軍隊の事等、多くの報道がありました。終戦時20歳の方が90歳を超えますので、戦時の事を語れる最後の機会となりました。私も68歳となり、そろそろ自分の記憶を纏めておいた方が良い歳となりつつあります。娘から私の父の戦争体験を聞かれ、一言では話しきれない多くの話がありましたので、文書に纏めて見たいと思いました。父も73歳で亡くなりました。私も父が亡くなった歳が近くなる事を感じて、父から聞いた戦争体験を、子や孫に書き残して置こうと思いました。
私の聞き違い、記憶違い、父の主観など、歴史事実と異なる事があるかと思いますが、あくまで父の語りを聞いた話として御容赦ください。
父は大正7年、大阪府堺市で辻田文平の7番目の子供として産まれました。商業学校では成績が良かったので、1番目の兄貴からの援助もあり、横浜専門学校に進学致しました。現在の神奈川大学となります。
当時の横浜専門学校は簡単な作りの校舎で、壁が紙で出来ていたと言っていました。圧縮ファイバーの様な物でしょうが、殴れば簡単に穴があき、防音効果もない壁だったそうです。ただ教授陣は一橋大学の教授が講師として来ていて、質の高い経済学を学ぶことが出来たそうです。父は一橋大学教授で後に学長となった近代経済学者の中山伊知郎氏に師事して、統制経済学を学びました。
折から昭和12年からの、支那事変が続いていました。国家が戦時下で経済的に円滑に活動していくには、市場済下でも企業に一定の制限をかける必要があると言う考え方でした。市場の価格調整に任せるのではなく、原料原価、労働対価、適正な利潤を加味して各造兵廠に納品される兵器、物資の価格を、経戦中と言う限定期間制限しようと言うものでした。社会主義国家では生産手段が公有となりますが、私有の生産手段を認めつつ、納品価格に一定の制限をかけて、継戦に必要な物資を円滑に生産しようと言う考え方でした。
昭和14年、横浜専門学校を卒業章と言う年に、中山教授から陸軍省経理部に入らないかと言う打診がありました。当時としては理想的な就職ですので、父も同意して陸軍省経理部への就職が内定しました。
それからが大変でした。父の下宿も実家も、憲兵隊が来て徹底して身辺調査しました。父の下宿に憲兵隊が来たときは、専門が統制経済学でしたので、同じ統制経済であったマルクス主義経済学の本も参考文献としてありましたので、あわてて本を隠したそうです。堺市の実家の方でも、父が横浜で何かしでかしたのではと心配していましたが、陸軍省に就職が決まったと聞いてとても喜んでくれたそうです。
陸軍省時代
こうして父の陸軍省経理部への勤務が始まりました。判任官だと言っていましたので、軍属であり、下士官クラスといった所でしょう。勤務当時は3ケタの連隊番号を持つ連隊が、次々新設されていました。連隊長と連隊旗手が皇居に参内して連隊旗を拝受して、その足で陸軍省玄関来て、連隊旗を掲げて挨拶致します。新設連隊の軍旗が到着するたびに軍属の雇員が鐘を鳴らして「軍旗――」と叫んで廊下を通ります。手のあいた陸軍省職員は全員陸軍省玄関に行き、軍旗の出発を祝いました。
父から軍旗小隊の話を聞きました。出征部隊と共に軍旗は移動しますが、宿泊が旅館であっても軍旗小隊は編上靴のまま座敷に上がります。座敷に軍旗を据えて、24時間軍旗の傍での警護が行われました。睡眠、食事もありますので3交代ですが、軍旗小隊員は食事も睡眠時も、完全軍装、編上靴を履いて巻脚絆を巻いたまま食事をし、睡眠を取るそうです。非常時は直ぐに軍旗を守る体制を取っているそうです。
父に軍旗の製造価格を聞いたことがあります。「軍旗は西陣織だから・・・」しばらく暗算をしていて、「100万位かな。」と言っていました。40年ほど前の話ですから、今なら4-500万円でしょうか。当時の最高の技術で作られるそうです。古い軍旗は旭日の部分が破れて無くなっていますが、あれはシルクの劣化のせいで、決して銃弾が開けた穴では無いそうです。シルクは50年ほどで生(しょう)が無くなると言われ、簡単に破れる様になるそうです。綿、麻ならその様な事は無いそうですが、幕末官軍の錦の御旗が西陣織を使った伝統でもありますから、承知の上で使用され続けたのでしょう。ちなみに海軍の軍艦旗は細番手のウール製で、備品扱いでしたので破れたら新しいものに取り換えます。
当時の陸軍省はネズミが多く、退出する時に2つの椅子の間に定規を置いて、その下にバケツに半分ほど水を入れ、空き缶に入れた糊を浮かべておきます。ネズミが糊を食べようと定規の上から飛び降りると、バケツの水で溺れ死ぬと言う仕掛けだそうです。水を半分くらい入れるのがミソだそうです。
勤務して半年目に、満を持して統制経済の価格設定に入りました。陸軍に納品されている全ての物資の原料原価、労働対価、適正な利潤を計算して、ある日突然に納品価格の変更を決定し、実行されました。あわてたのは経営者たちでした。市場価格をしっかり調べられているので、文句の付けようが無かった様です。しかし「陸軍省はアカに占領されている」と、憲兵隊に訴えたられたそうです。憲兵隊から廻ってきた抗議文書の束を父の上司は放り投げて、「今さら何を言ってやがる」と、相手にしなかったと聞きます。
父の話では、その時に株をやっていれば大儲けが出来たと言っていました。もちろん陸軍省職員では出来る事では無いです。私も最初意味が判らなかったですが、陸軍省の統制経済政策が実行されれば株は大暴落します。しかし、落ち着いて考えると企業の経営力はしっかりとありますので、株は反発して元の価格近くまで戻ります。この暴落時に株を買って、反発して戻った時に株を売るのではないかと思いました。
陸軍省勤務は、1年ほどで終わりました。父は多くは語りませんでしたが、業界の反発を逸らすために、統制経済企画を作ったチームを解散させたようです。父にも徴兵が来て、二等兵としての帝国陸軍軍人時代が始まりました。陸軍省に勤務しても、兵隊では二等兵と言うのが良く理解できませんでしたが、軍の組織ではその様になるそうです。
→兵隊時代へ続く
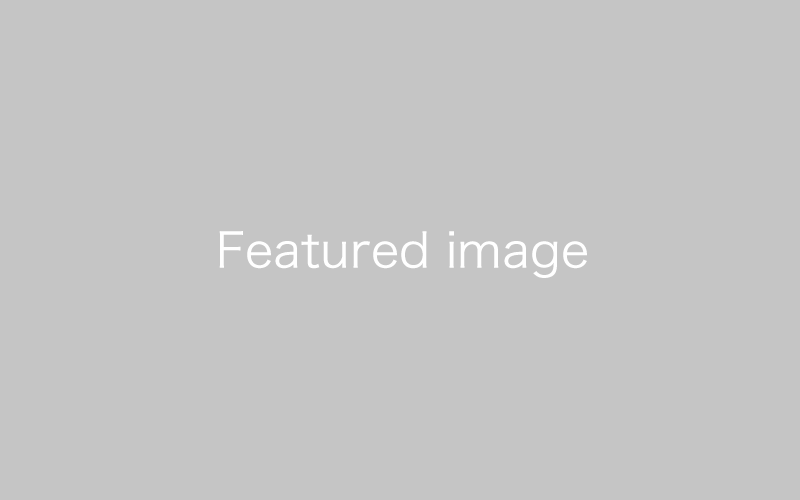


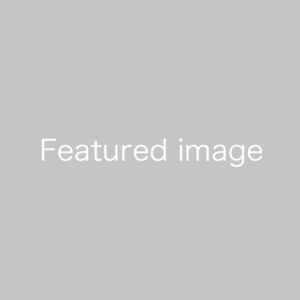
コメント